俳句的生活(223)-虚子の詠んだ京都(1)嵐山ー
世間一般には余り知られていませんが、高浜虚子は19歳から21歳までの多感な青春時代の2年間を京都で過ごしています。京都は虚子が郷里松山を出ての初めての異土で、彼の文学的心象に多大な影響を与えたことは、以後60年間、太平洋戦争中の数年を除き京都を訪れない年は殆ど無かったことでも明らかです。
明治25年9月、松山の中学を卒業した虚子が向かった先は、京都の第三高等学校、現在の京都大学教養部(平成5年より総合人間学部)でした。すでに京都での帝国大学の創立は決まっていて(明治30年創立)その布石として位置づけられていた学校です。校舎は次の写真のように、レンガ造りの立派なものでした。
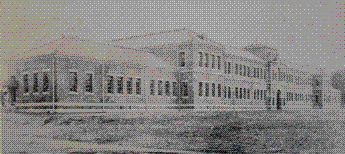
この時代の虚子の写真も残されています。

三高時代の虚子は、2年の間で下宿を5回ほど変えています。2番目の聖護院近くの下宿の時、京都に来てから2か月後のことですが、そこに東京帝国大学を中退し、日本新聞社に入社したばかりの正岡子規が訪ねてきました。この時二人は二里の道を歩き、嵐山で屋形船をやとい、茶店より料理を運ばせて、大堰川を上り下りしています。二人が語りあったのは当然文学のことで、このときの遊びを、子規が「あの時ほど身分不相応の贅沢をしたことは無い」と後年語ったということを、虚子は回想しています。
この嵐山での出来事は、虚子に深い印象を与え、その後何度も嵐山を訪れて句を残しています。
花に消え松にあらはれ雨の糸 虚子(昭和7年)

この句は恐らく、桜と松の両方が見える渡月橋あたりで作られたものと思います。京都の春の細やかな雨が、桜を前にしては淡い花の色に溶け込み、緑の松を前にしては、はっきりと浮き上がって見えるという句です。
舟ゆくがまゝに緑の嵐山 虚子(昭和18年)

嵐山の緑が、大堰川を緑に染めています。
明治25年は、子規が新聞「日本」で月並み俳句批判を開始し、発句を俳句と改称した年で、まさに「俳句元年」と呼ぶにふさわしい年でした。この年に虚子が三高の一年生であったということも、何かの縁を覚えます。
ぬるぬるの鵜照らす火や京の川 游々子


